今ぐらい暑くなってくると、スイカが美味しい時期になってきましたね。
実は本日、7月27日は「スイカの日」なんです!
生活していて「スイカの日」は、あまり聞きなじみがないですよね。
今回の記事では、なぜ7月27日を「スイカの日」と制定したのか、スイカに関する雑学も紹介いきます!
7月27日がスイカの日になった由来

7月27日をスイカの日とした由来は2つあり、まず1つ目はスイカが最も美味しくなる季節が7月から8月であること。
そして、2つ目はスイカの縦縞模様が「綱」に見えることから、綱 (つな)=27の語呂合わせから7月27日をスイカになりました。
スイカの縞模様を綱(つな)に見立て、7(な)つの2(つ)7(な)=「夏の綱」の7月27日に。
そして、回文にもなっているのがユニーク!(どっちから読んでもなつのつな)
面白いことに「スイカの日」は、スイカの愛好家グループによって制定された記念日なんです。
今では縦縞の入ったスイカが一般的ですが、縞模様の入ったスイカが出回るようになったのは昭和のはじめ頃と割と最近。
それまではボーリング玉みたいな、黒一色の無地皮のスイカだったようです。
7月27日がスイカの日になった由来 漢字の由来
スイカは漢字で「西瓜」と書きます。
「西瓜」は中国であてられた漢字が日本に入ってきたもの。
その語源は、中国から見て西側の「ウイグル」から伝わります。
なので、「西から来た瓜」で「西瓜」になりました。
スイカの原産国であるアフリカでは、紀元前5000年頃には既に栽培されていたそうです。
10世紀に中国へ伝わり、16世紀後半に日本へやってきました。
採れたてや産地の違う物は一味違うので、いろんな産地のスイカを味わってみたいですね。
7月27日がスイカの日になった由来 公式ルールのスイカ割り

夏の海でやりたい定番のイベントのスイカ割り。
お祭りや地域のイベントでもスイカ割りを見かけますし、海水浴場ではより一層楽しめますよね。
そんなスイカ割りに、なんと公式ルールがあるんです!
農業協同組合(JA)の設立した、日本すいか割り協会(Japan Suika-Wari Association)という団体が1991年にスイカ割りの公式ルールを制定。
まず、スイカと競技者の間の距離は9m15cmです。
使う棒は直径が5cm以内で、長さが1m20cm以内。使用するスイカは国産でよく熟れたもの。
制限時間は3分で、スイカを割る競技者が複数いた場合はスイカの断面の美しさで判定します。
最も得点が高いのは均等にスイカを2つに割った場合で、大きさが不均等だった場合は減点法によって採点。
ぜひ公式ルールに則って、スイカ割りを楽しんでみてください!
7月27日がスイカの日になった由来 おいしいスイカの選び方・食べ方
・スイカは模様が濃い(甘い)
・へその部分が緑色
・へそ部分がへこんでいる(熟してる)
八百屋さんやスーパーの店頭で、スイカを購入する場合は「へそ」に注目!
へそというのはスイカのツルがついているところ。
スイカの最適温度は15℃くらいなので、常温で涼しいところに置いておきたいです。
冷蔵庫で冷やすと風味が落ちるので、なるべく早く食べきるのがベスト!
普段、スイカの赤い実の部分だけを食べていませんか?
赤い実と外側の皮の間の白っぽい皮の部分だけの状態にして、細くスライス。
糠(ぬか)や塩に軽く漬けることで、さっぱりとした浅漬けができます。
糠につければ栄養価も上がるので、皮だけ残ったスイカでお試しあれ!
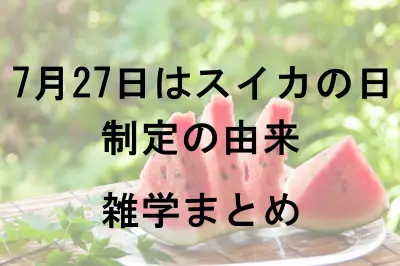
コメント